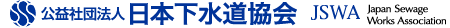下水道施設耐震計算例―管路施設編―質疑応答集
1. 耐震計算の基本的事項
- 問1.1 「重要な幹線等」と「その他の管路」について
- 問1.2 耐震設計の検討項目と参考文献について
- 問1.3 重要な幹線等はレベル2照査のみか?
- 問1.4 本計算例の指針としての位置付けについて
- 問1.5 レベル2地震動の設定方法とマグネチュ-ドについて
- 問1.6 レベル1,2の震度階級について
- 問1.7 ダクタイル鋳鉄管(圧送管)のみ水道耐震指針を用いた理由について
- 問1.8 被害実態との整合性を判断する方法について
- 問1.9 基盤層の設定方法について
- 問1.10 基盤層を20mとしてよいか?
- 問1.11 基盤層が深い場合の対策について
- 問1.12 炭坑地区の基盤層設定方法について
- 問1.13 レキ質土や玉石混土の基盤面について
- 問1.14 砂と粘土の中間土質の基盤層について
- 問1.15 耐震計算に必要な土質試験について
- 問1.16 既存土質資料の利用について
- 問1.17 PS検層の必要性について
- 問1.18 Ts<0.1の場合のSvについて
- 問1.19 N=0の場合のVsiについて
- 問1.20 N=0の場合のバネ値について
- 問1.21 土荷重の考え方について
- 問1.22 緩み土圧について
- 問1.23 各係数の算出方法と経済性について
- 問1.24 地盤反力係数算出時のαについて
- 問1.25 近似式の採用について
- 問1.26 レベル1の耐震検討項目について
- 問1.27 製品長の考え方について
- 問1.28 地盤バネの作用方法について
- 問1.29 基盤層に近い地盤バネが最大となることについて
- 問1.30 「ガス導管耐震設計指針」との整合について
- 問1.31 設計応答速度式について
- 問1.32 TGからTSを求める際の係数1.25について
- 問1.33 耐震設計マトリックス表について
- 問1.34 土圧計算の過程について
- 問1.35 埋戻し土の土質設定について
- 問1.36 埋戻し土の単位体積重量について
- 問1.37 地盤改良した場合の地盤バネについて
- 問1.38 地盤改良層における永久ひずみについて
- 問1.39 常時土圧の考え方について
- 問1.40 人孔接続部の屈曲角について
- 問1.41 常時のせん断力分布について
- 問1.42 ランキンの主働土圧使用について
- 問1.43 円形管のバネ定数低減について
- 問1.44 近似式の動的ポアソン比導入公式について
- 問1.45 耐震設計マトリックス表の○印について
2. 管の耐震計算
- 問2.1 マンホールと本管接続部の許容値について
- 問2.2 曲線推進部の抜出し、管体応力について
- 問2.3 塩ビ管の液状化対策について
- 問2.4 立坑空伏せ部や固定支承の計算方法について
- 問2.5 推進工における可とう管の必要性と設置位置について
- 問2.6 各抜出し量の累加による照査か?
- 問2.7 マンホールから1本目の継手までの距離について
- 問2.8 剛性管の軸方向応力の考え方について
- 問2.9 自動車荷重の考え方について
- 問2.10 推進工法における管種の使い分けについて
3. 液状化関連
- 問3.1 レベル1,2とタイプⅠ、Ⅱの関連について
- 問3.2 液状化判定を必要とする地震レベルについて
- 問3.3 γi1、γi2、γユ i2について
- 問3.4 液状化地盤の土質定数低減について
- 問3.5 レベル1における沈下率について
- 問3.6 永久ひずみを考慮する条件について
- 問3.7 埋設管と液状化層の位置について
- 問3.8 液状化時のマンホール沈下について
- 問3.9 液状化時の過剰間隙水圧について
- 問3.10 液状化時の浮力について
- 問3.11 液状化対策について
4. 計算モデル
- 問4.1 常時荷重として考慮する荷重について
- 問4.2 常時断面力と地震時断面力の合計値による照査について
- 問4.3 本計算モデルと近似式の比較について
- 問4.4 地盤変位は単層地盤でバネ値は複層地盤について
- 問4.5 耐震診断手法について
- 問4.6 計算モデルの支点について
- 問4.7 安全係数について
- 問4.8 管種の許容安全率について
- 問4.9 両側載荷の支点について
- 問4.10 基礎支承角の考慮について
- 問4.11 引抜きの付加土圧について
5. 計算例以外の耐震計算手法
- 問5.1 推進工法の立坑空伏せ部について
- 問5.2 鋼製サヤ管方式について
- 問5.3 開渠について
- 問5.4 レベル1における液状化対策について
- 問5.5 基盤層の途中にマンホールや管路がある場合について
- 問5.6 支持力計算について
- 問5.7 水管橋や橋梁添架について
- 問5.8 圧送管管種について
- 問5.9 内形と外形が異なる場合について
- 問5.10 離脱防止金具や特押管の計算について
- 問5.11 圧送管に塩ビ管を使用する場合について
- 問5.12 接着継手の塩ビ管が人孔到達する場合について
- 問5.13 計算例に無い材料について
- 問5.14 本管と取付管接合について
- 問5.15 沈埋工法の計算について
6. 可とう継手関連
- 問6.1 掲載されている可とうマンホール継手の選定条件について
- 問6.2 接着継手の塩ビ管への可とう継手の必要性について
- 問6.3 空伏せ工と人孔接続部への可とう継手の必要性について
- 問6.4 副管と人孔接続部への可とう継手の必要性について
- 問6.5 ケーシング立坑やライナープレートへの可とう継手の必要性について
- 問6.6 抜出し量小の場合の可とう継手の必要性について
- 問6.7 PC・RCボックスカルバートの可とう継手製品について
7. ボックスカルバート
- 問7.1 設計水平震度について
- 問7.2 地震時振幅荷重時について
- 問7.3 荷重の載荷方法について
- 問7.4 頂版部の周面せん断力について
- 問7.5 基礎地盤が基盤層の場合について
- 問7.6 せん断応力度の割増について
- 問7.7 斜切製品使用の場合について
- 問7.8 斜形連結の考え方について
- 問7.9 地盤反力係数算出時の奥行きBについて
- 問7.10 小口径Boxの縦締め方法について
- 問7.11 既製ボックスカルバートのスパン長について
- 問7.12 慣性力について
- 問7.13 耐震計算の必要性について
- 問7.14 耐震設計マトリックス表について
- 問7.15 PC鋼材の緊張力照査について
- 問7.16 L2時の照査表における破壊モードの判定について
8. シールド
- 問8.1 等価換算剛性の算出における有効断面積と断面二次モーメントについて
- 問8.2 応力度照査がNGの条件と対応策について
- 問8.3 曲線部の検討方法と対策について
- 問8.4 マンホールとの接続部の許容値について
- 問8.5 抜出し量算出時の有効長をセグメント幅としていることについて
- 問8.6 鉛直断面の計算において剛性一様リングとしていることについて
- 問8.7 レベル2における鋼製セグメントの引張強度による検討について
- 問8.8 常時満水状態の慣性力の考え方について
- 問8.9 地盤急変部や液状化時の管軸方向応力度について
- 問8.10 管軸引張側の断面力を低減補正することについて
- 問8.11 軸圧縮剛性にボルトまで考慮したことについて
- 問8.12 地盤バネの考え方について
- 問8.13 JSWAS A-3,4-2001との整合性について
9. マンホール
- 問9.1 矩形人孔の構造計算手法について
- 問9.2 配筋手法について
- 問9.3 マンホールを特定しない場合について
- 問9.4 荷重の載荷方法について
- 問9.5 現場打ちと組立の組合せ構造について
- 問9.6 組立マンホール計算手法の妥当性について
- 問9.7 伏越し部内圧について
- 問9.8 計算手法の違いについて
- 問9.9 p.13-24の「+」と「-」について
- 問9.10 地盤反力係数の算出方法について
1. 耐震計算の基本的事項
-
問1.1
「重要な幹線等」と「その他の管路」の具体的な設定法を検討されているのか。「重要」,「その他」ではあまりに抽象的である。 - 確かに抽象的ですが、あくまでも「重要な幹線等」と「その他の管路」の区分は、基本的に「日本下水道協会;下水道施設の耐震対策指針と解説,1997年版」§3耐震対策の基本的な考え方(p.5)、§12耐震設計の基本的な考え方(p.29)に従い、地域特性、地盤特性及び施設の特性や規模ならびに類似施設の被災事例等を考慮して、各自治体の判断により決定するものです。なお、判断基準については、国土交通省の平成13年8月23日事務連絡により示されている通りです。
-
問1.2
1.「下水道施設耐震設計例-管路施設-(前編)」のp.18耐震設計の検討項目と参照文献(表1-4)について
表1-4(以後表)に耐震設計の項目が表記されている。その中の(差込継手構造管路)において、「その他の管路」についてはマンホールと管渠の継手部のみを耐震設計対象とし、管路本体、マンホール本体、管渠と管渠の継手部について耐震設計対象外としている。その理由が明確の場合は回答を頂きたい。
また、レベル1地震動において液状化する場合、地盤の永久ひずみによる抜出量、地盤の沈下による抜出し量についても「その他の管路」については検討項目から除外項目とするのか。
また、同じレベル1地震動に対する照査において、「重要な幹線等」では管渠と管渠の継手部(特に地盤沈下による抜出量)、管本体の検討、マンホール本体の検討について照査を行う理由について回答を頂きたい。 -
「その他の管路」は一般に復旧が容易であること、管路延長が膨大であること等の特質があります。それらすべてに対して高い耐震性能を確保する事は現実的でないことや、レベル1地震動に対して重大な被害を生じるおそれが少ないことからマンホールと管渠の継手部のみの検討で良いとなっております(指針p.30,32参照)。
レベル1地震動で液状化する地盤での「その他の管路」の継ぎ手性能の検討は行わなくて良いこととなっています。これは、永久歪みや沈下についての設計データがすべて、兵庫県南部地震のデータ(レベル2地震)に基づいているからです。レベル1地震時のデータは明確になっておりません。従ってその他の管路では、継ぎ手性能の検討は行わず、埋め戻し材を検討する等、液状化防止の検討を行うこととしたものです。
重要な幹線ではレベル1、レベル2の両方を計算する必要があります。これは地震レベルが異なると同時にレベル1とレベル2では管体の許容値、継ぎ手性能の許容値が異なるためです。
(例:ヒューム管ではひび割れモーメントと破壊モーメント等)
また永久歪みに関しては、前述の事由から、レベル2のみとしますが、液状化に伴う地盤沈下に関しては、沈下率はレベル1,レベル2とも同様として継ぎ手性能を検討します(但しレベル1とレベル2では液状化層厚が異なる場合があります)。 -
問1.3
重要幹線の場合、レベル1の検討後レベル2の照査となっていますが、(使用限界状態と終局限界状態と設計法が違うからかもしれないが)レベル2の照査でOKならばレベル1もOKとはいえないのか。レベル2の照査だけではいけないのか。 -
「レベル1検討は必要」です。
レベル1検討では地震動も小さくなりますが、チェックするときの許容値も小さくなります。具体的には、ヒューム管の管体ですとレベル1についてはひび割れ保証モーメントですし、レベル2では破壊保証モーメントでチェックすることになります。抜け出し量や屈曲角も、レベル1検討ではレベル2許容値の1/2としています。 -
問1.4
本計算例は、計算例とされていますが、指針としての位置づけはなされているのか。 -
本計算例は、指針(1997)を補完するものです。
「指針」の発刊以来、実際に「指針」に基づいた管路施設の耐震設計を行った下水道実務者からは、数々の意見や質問が寄せられてきました。 たとえば、2段階の設計対象地震動と検討項目の使い分けがわかりにくい、「指針」では耐震計算例が少なく様々な管種と計算手法が明確でない、応答変位法による鉛直断面方向の断面力が大きくなりすぎる等が代表的なものでした。このような指摘事項を配慮し、 また指針発刊以来の耐震設計の技術的進歩、実際の被災事例との計算結果の整合性をふまえて指針を補完する役割としての計算例をとりまとめたものです。 -
問1.5
レベル2地震動は、それぞれの地点において応答速度の推定が可能な場合にはその大きさを用いる、とあるが、以下のことを教えていただきたい。
[1] 推定の方法
[2] レベル1および2は想定震度またはマグニチュードで判定すると、どの大きさに相当するのか。
[3] 今後、重要な幹線において地域性を考慮するには、どの様な設定を行なえばよいのか。 - [1]について
推定の方法はいろいろあります。
土木学会の開削トンネルの耐震設計などを参考にされたい。一般的な流れとしては、
・想定地震の設定(既往の被害地震や活断層)。
・断層モデルから地震規模を想定。
・距離減衰式により、最大加速度や応答スペクトルといった地震動の特性を設定。
・過去の強度記録等から、位相差(特性)を与えて時刻歴波形を作成。
といったところとなります。
[2]について
レベル1、レベル2地震動と、震度またはマグニチュードとの明解な関係は示されていません。なお、震度は表層地盤の特性を反映したうえでの揺れを表す指標なので、地震動レベルとの関係は一律に定まりません。また、マグニチュードに関しても地域によって想定される地震が異なるはずなので、一律には地震動レベルとの関係は定まらないと考えられます。東京周辺で言えば、レベル2地震動はマグニチュード7~8クラスとされています。
[3]について
地域性を考慮した場合は、当該地域での想定地震を調査して設定すればよいこととなりますが、指針の応答速度スペクトルを用いることがあくまでも基本です。
-
問1.6
耐震設計のレベルについてですが、地震動レベル1、レベル2を気象庁の震度階級に照らし合わせるとどのくらいの震度になるか教えて頂きたい。また、文書で表記されているならば、文書名を教えて頂きたい。 -
耐震設計の改訂思想は、土木学会の「土木構造物の耐震基準等に関する第二次提言、1996年1月10日」におけるレベル1・レベル2の考え方が基になっています。ここには、マグニチュード7級の地震をレベル2として導入することが記載されています。
これを受け、日本下水道協会では「下水道の地震対策についての第一次提言、第二次提言、最終提言」において、耐震設計においてレベル1・レベル2を導入したことを述べています。
(これは「日本下水道協会;下水道の地震対策についての検討報告書(概要),平成9年8月」の巻末資料に掲載)
一方気象庁は、1995年11月29日付で震度階級を見直しています。つまり両機関共ほぼ同時期の見直しですが、地震動レベルと震度階級との厳密な関連はとられていません。レベル1・レベル2は、あくまでもマグニチュードを基本にしたものです。
したがって、あくまでも目安の意味でレベル1・レベル2が震度階級でどの程度に相当するかを回答します。一例ですが、「日本下水道協会;下水道の地震対策マニュアル 平成9年(1997年)」では、「本マニュアルは気象庁震度階級5(弱)以上の地震の事例を参考にして作成した。(p.5)」、また「本マニュアルは、これらの地震の事例に加えて、震度Ⅶの大都市圏直下型地震である兵庫県南部地震(平成7年 マグニチュードM=7.2)等による被災および復旧状況を参考に作成した。(p.6)」と記載されています。
以上より、あくまでも地震動との明確な関連はないですが、あえて関連づけるとすればレベル1はおおよそ震度階級5(弱)以上、レベル2はおおよそ震度階級7相当と考えることもできます。 -
問1.7
ダクタイル鋳鉄管(圧送管)の耐震計算方法は「水道施設耐震工法指針・解説」に準じ行うとあり、設計応答速度スペクトルも水道耐震指針のものを用いて行っている。 耐震計算方法だけ水道耐震指針に準拠して、設計応答速度スペクトルは下水道耐震指針のものを用いたほうが、他の管種の耐震計算との整合がとれてよいと思うが。 ダクタイル鋳鉄管(圧送管)の耐震計算に水道耐震指針の設計応答速度スペクトルを用いた理由を教えていただきたい。 - ダクタイル鋳鉄管(圧送管)については、水道施設への採用実績が圧倒的に多いことから、設計外力、許容応力等も圧送管の震災時の影響等を考慮し検討された、 「水道施設耐震工法指針」に準じることとしたものです。同じ圧送管で計算結果に差が生じると使用する側で混乱するため、水道施設耐震工法指針の設計応答速度スペクトルを使用することとしました。
-
問1.8
「計算結果が実体とかけ離れている」という問題を、「計算例」を作成した目的の一つとして挙げてあるが、今回の「計算例」作成により、上記の問題はどの程度改善されたのか。例えば、実際に被災した管路のデータをもとに計算をして「被災する」という結論がでてくることを検証されたのか。
「計算結果が実体と整合する」又は「計算結果が実体とかけ離れている」ことを判断する方法はないのか。 -
指針巻末の計算結果と実態が整合していないと思われるのは鉛直断面の検討です。
鉛直断面の検討において、見直しを行ったのは以下の項目です。
[1] 荷重載荷モデル(両側載荷←片側載荷)
[2] 地盤反力係数(地盤バネ)算出時の計算条件
<どの程度改善されたか。>・ 係数 α=1(←α=2) ・ 奥行き方向換算載荷幅B =製品長 =10m(シールド、現場打ち矩形渠) (↑単位長さ1m)
・指針巻末の計算方法では、特にヒューム管において一般部であってもレベル2検討時に発生モーメントが破壊保証モーメントを上回るケースが見られました。このようなケースについて計算例の方法で再計算してOKを確認しました。
・兵庫県南部地震(1995)において、鉛直断面の被害を生じなかったケースで、入手できたデータに基づいて指針巻末の方法で計算したところ、大きく破壊保証モーメントを上回るケースがありました。これを計算例の方法で再計算したところ、OKを確認しました。
(なお、兵庫県南部地震時に鉛直断面で被害を受けた事例は報告されていません。)
<判断する方法。>
基本的には、実際の被害状況と解析モデルや計算条件を比較検証し、精度の向上を図っていくことが必要と考えます。 -
問1.9
基盤層を設定するための考え方と調査について具体例があれば、説明していただきたい。 -
耐震上の基盤面とは、地震波形の変化が少なく、一様に周囲へ伝播し得るような強度の高い岩盤をいいます。
本来の地質学でいう基盤層とは、一般にせん断弾性波速度VsがVs≒3km/sの強硬な岩盤を指しますが、土木分野ではある程度Vs値が小さくても、構造物が常時の設計強度で耐え得る点を踏まえ、Vs≧300m/sで割り切っているのです。これはN値でいえば、粘性土;N値≧25、砂質土;N値≧50に相当します。
このように考えると、耐震基盤面とは、所定のVs値あるいはN値が以深へ連続していることが必要で、たとえば軟弱層中の締ったレンズ状の砂層は、杭の支持層にはなっても耐震基盤面としては該当外になるわけです。こうした地盤の強度の連続性を確認するためには、ボーリングによる調査、ダム地質で行うような弾性波深査があります。 しかし、一般的には既存のボーリングデータに基づく基盤面の面的な分布確認,広域的な地質図による確認など室内作業における検討も加え、なるべく経済性を図る調査計画が必要です。
なお、地質学的基盤層と耐震基盤面との違いについては、「地盤工学会編;技術手帳3,p.67」に嶋悦三氏(東京大学名誉教授)による解説が記載されています。 -
問1.10
実際の原位置試験(ボーリング調査)で基盤層まで調査する必要があるか。調査費用その他の面で基盤層まで調査できない場合、以下の仮定により20mを基盤層としてよいか。
せん断弾性波速度≧300m/sとは洪積層が中心と考えられる。
↓
液状化の判定で「20m以内の飽和層」の場合は判定が必要と書いてある。この条件は、主に液状化する層が沖積層中心で生じると捉えることができる。
↓
よって、液状化の判定に使用している20mとは、沖積層と洪積層との境界であると考えられる。
↓
したがって、地盤下20mを基盤層としてもよいと思われる。 -
液状化の判定で下限値とされている20mは、過去の液状化の事例から20m以深は考慮しなくてもよいとの判断で定められているものであり、沖積と洪積の境を20mとしているという意味ではありません。
したがって、液状化の下限値(20m)を基盤層と説明することはできません。
全てのボーリングを基盤層まで実施する必要はなく、応答変位法で「ここを基盤とした」と説明できる資料があればよいと思われます。
具体的には、他事業でのデータや地形図、地質図などから想定することも可能です。
基盤層は、弾性波速度≧300m/sとなる位置を確認する必要があります。又、基盤層は何m確認すれば良いという数値は今のところないので、地域全体での地層構成図や、既往土質データなどをもとに、概略の基盤層コンターを作成しておけば、それを利用して新規の土質調査計画を立てることができます。 -
問1.11
基盤面が非常に深い場合の対処方法について。 -
基盤面が非常に深く、どこまで掘っても基盤層が出ない場合の対策ですが、応答変位法による耐震設計では、管の抜出し、屈曲角については基盤層がかなり深い場合でも、許容値を満足します。応力的には、管の埋設深度が浅く基盤層がある深度以上になると、相対変位がほとんど変わらなくなるので、それ以上基盤層を深くしても応力的な変化がない状態があります。その応力的に結果が変わらない基盤層位置が見つかれば、それ以上確認する必要がないこととなります。
ただし、縦断方向の応力検討を行うボックスカルバートやシールドはこの限りではないので注意が必要です。 -
問1.12
炭坑地区のように、基盤層と判断できる層が数m確認されても、その下層に古洞が出現することがある。このような時はどの位置(層)を基盤層とすれば良いのか。 -
空洞がある場合については、その空洞の大きさや基盤面との位置関係、設置する管の大きさ、両者の相対的な位置関係、管の重要度などにより考え方が異なると考えられます。
空洞が小さかったり、基盤面よりもかなり離れている場合には、計算例で示した方法で問題ないと思われます。空洞を無視できない場合には、空洞の下方に仮想基盤面を設定し、動的解析により地盤変位を求めることができますが、そこまで実施するか否かは、管の重要度などから判断することが必要です。 -
問1.13
レキ質土・玉石混土の場合の基盤面の考え方を教えてほしい。
(標準貫入試験では、レキ又は玉石等に当たってN値が50以上でることがあるがこの地盤を基盤面としてよいか。) - このような層の場合、N値は比較的大きくでますので、N値だけで判断せず、工学的に判断してください。(せん断弾性波速度が300m/s程度以上)
-
問1.14
N値35の砂質シルトは基盤層として扱えますか。砂質に近い粘性土層(N>25の適用でOKか。) - 基盤層の定義は粘性土層か、砂質土層か、しかありません。正確には実測して、せん断弾性波速度が300m/s以上となればよいこととなります。 N値で判断する場合は、粘性土と砂質土の中間的土質については今のところ担当技術者の判断で決定するしかありません。
-
問1.15
耐震計算に必要な土質試験(室内)の項目について。管路部及び管路上部・下部における耐震計算に必要な土質試験項目はどんなものがあるか。また、管路部においては、三軸試験(C,φ)は必要か。ボーリングのピッチはどの程度が標準か。 - 試験項目については、土層毎が原則と思われます。管路上・下部で同一の場合はあえて、2ヶ所は不要となります。三軸試験については、液状化に対抗するせん断抵抗値を求める際に参考となりますが、前述のように土層毎に求めるのが良策です。尚、試験の手順、試験項目等は指針第1章総論の第3節に詳細な記述がありますが、予備調査→本調査→液状化調査等の手順を踏むのが理想的であると思われます。土質試験計画に際しては、近隣、既設データ等を十分に検討されて計画されることが有効と思われます。
-
問1.16
指針では基盤面の確認に関して、既存資料により効率的な新規土質調査計画が図られるとあるが、一般的に耐震検討を行う際に既存土質データ箇所よりどの位離れていても使用可能か。 - 一概には言えません。広い範囲での地層構成をみて判断するしかありません。地層の変化が著しい場合は出来るだけ近接したデータが必要となり、地層構成やN値の分布にそれほど変化が無い場合は想定地層断面図でもOKです。
-
問1.17
土質調査を計画する場合、PS検層は不要か。また、PS検層値がある場合、N値からの推定値とどちらを優先させるべきか。(N値で全て計算できるなら、PS検層は不要と思われる。) - 特に重要な構造物ではPS検層を調査することとなっていますので、基本的にはPS検層は必要であり、PS検層値があればそれを優先させるべきです。ただし、実用上は、せん断弾性波速度Vsやバネ値を地盤のN値で算定できるようにしておりますので、通常の地盤条件であればあえてPS検層を行う必要はないでしょう。
-
問1.18
レベル2の設計応答速度(Sv)を算出する際、表面地盤の固有周期(Ts)が0.1以下になる場合の固有周期(Ts)の数値の取り扱い。 -
設計応答速度スペクトルで、横軸(固有周期Ts)がグラフ左端からはみ出すためSvが求められないとの質問と思います。左からはみ出す部分は、描かれているスペクトルの直線をそのまま延長して、グラフを補完して求める以外ありません。安全を考えるなら、左端の目盛りTs=0.1秒でのSvの値を用いる場合もあり、ケース・バイ・ケースです。
(補足 Ts≦0.1秒となるケースについて)
(1) 地盤の状態地盤の特性値TGと地盤種別の関係でいえば、Ts=1.25・TGですから、Ts<0.25秒であれば I 種地盤に相当します。
では、 I 種地盤とはどういう地盤であるかというと、「洪積層の良好な地盤、ないし岩盤(軟岩相当)」です。つまり、Ts≦0.1秒では I 種地盤の中でも非常に良好な状態、つまり硬質岩盤に相当するわけで、本来ならば耐震設計の範囲外となります。
一応、設計速度スペクトルTs~Svグラフは、耐震設計が必要と思われる範囲を一応想定してグラフにしているわけです。
(2) 表層地盤の厚さまた、計算上Ts≦0.1秒となる場合として、表層地盤の層厚が極端に薄い場合は、それが軟弱であっても I 種地盤に該当する場合があります。たとえば、層厚0.5m×1層,N値=1,Vs=100m/sの軟弱粘性土では、TG=4Σ(H/Vs)=4×0.5/100=0.02秒となり、 I 種地盤となります。この場合は、まずは本当に表層地盤内に管路施設が位置するのかどうかを確認することが必要でしょう。 -
問1.19
Vsiの実測値が無いN=0(モンケン自沈)の土質の場合、Vsiを求めるにはどうするか。 - Vsi(平均せん断弾性波速度)は、粘性土で1≦Ni≦25,砂質土で1≦N≦50が適用範囲になっており、N=0の場合、N値による算出はできません。従って、弾性波速度を実測するのが最も良いわけですが、あらためて実測するのが難しい場合、「道路橋示方書・同解説(ⅴ耐震設計編)」により、粘性土、砂質土にかかわらずVsi=50m/sとして計算を行います。
-
問1.20
N値が0(ゼロ)の地盤の地盤バネの設定はどうしたらよいのか。 -
N値が0(ゼロ)であると、N値に基づく推定式が適用できません。また、こうした超軟弱地盤ではボーリング孔壁が乱れるため、孔内水平載荷試験の実施も難しく、また不攪乱試料もサンプリングできないので、地盤の強度定数は一般的な土質試験方法(一軸圧縮試験など)では求めることができません。
こうした場合、原位置ベーンせん断試験,オランダ式二重管コーン貫入試験などのサウンディングを行うことがあります。ただし、サウンディングでは、地質・土質構造の判別に重要な要因となる地層境界確認などの目視情報が得られないため、ボーリング調査との併用が必要です。詳細は「地盤工学会編;地盤調査法」などを参照して下さい。
地盤バネ値の設定では、こうしたサウンディングによって求められた値(ベーンせん断試験では直接的に粘着力c,他のコーン試験はコーン指数qc)から、各種の換算式により変形係数Eを推定することが必要です。
なお、こうした特殊な調査方法を省略したい場合、構造物の重要性により発注機関と協議の上で、N値=1として計算した結果を検証する方法もあるでしょう。 -
問1.21
なぜ開削は全土圧で推進等は緩み土圧を採用するのか。地震で地盤が変位するにもかかわらず、緩み土圧の範囲は変わらないのか。埋設直後なら別ですが、埋設して何年かたてばどちらも地山とほとんど変わらなくなるのではないか。 - ご指摘のような考え方も当然ありますが、本計算例では、常時の荷重は従来通りとし、それに地震時の荷重を加えて計算することとしました。従って、開削は全土圧、推進は緩み土圧を採用しております。
-
問1.22
緩み土圧について
推進管の場合、常時荷重に用いる上部土荷重には、緩み土圧を考えることになっているが、レベル2地震動のような大きな外力が作用した場合でも、緩み土圧を考えてよいか。
管の周辺が液状化するような場合、地震の終了後には管頂部には全土被り荷重が作用するように思える。仮に、地震の最中には緩み土圧が考えられる場合があったとしても、地震終了後には土のアーチ作用が崩れて砂質土でも直土圧が作用するものとして計算したほうが現実的ではないか。 -
液状化する地盤における緩み土圧の考え方は研究途上の分野であり、本計算例の中で明確な答えは見出せませんでした。ご質問にあるように、液状化する地盤は一時的には土のアーチング効果は崩れることが考えられます。一方、液状化すれば土圧よりも浮力の影響が大きいという指摘もあります。もろもろの未確定の要素があり、地震時の荷重に考慮する常時の荷重は本計算例では変更しないことにしました。
-
問1.23
N値により各係数が決定されているが、現場・室内試験からせん断弾性波速度などの係数を評価することにより、経済的な設計が可能か。可能であれば最も効果的な試験、着目する係数等を教えてください。 - 今回の計算例集では、実務上から考えて、今までの常時の設計時の土質調査を生かせるようにしています。ただし、重要な構造物については、各種土質試験から各係数を求める必要があり、場合によっては経済的になることも考えられます。なお、試験項目については指針第1章 総論の第3節を御参照ください。
-
問1.24
管の鉛直断面計算において、地盤反力係数算出時にα=1とすることについて、もう少し詳しい説明が欲しい。α=1とすると、管の発生応力が半分となり、結果的にレベル2地震動においても全く被害が生じない結果となり、過小な応力になっていないか。「大規模ガイドライン(案)」に、FEMを用いたバネ定数の算定手法が示されているが、このような検討は行われたのか。 また、実際のヒューム管は協会規格の耐荷力に対して2~3割の余裕があると考えられないか。 -
α=1とした理由については、第1章 耐震概要編p.21に示した通りです。あくまでも、本計算例はできるだけ実務的に計算可能な手法を示したもので、FEMによるバネ値の算定等、本計算例以外の手法もありますのでご検討ください。
なお、神戸市のご協力も得て、本計算例の手法で試算を試みた結果、被害実態と試算結果は整合性があるとの判断ができるものでした。
全国ヒューム管協会では、現段階でヒューム管の破壊荷重に余裕があることを保証できないとの見解ですので、今までの値を使用してください。 -
問1.25
近似式で用いている補正係数β=1.3は安全側すぎ、1.0が妥当であると思われるのでβ=1として近似式を用いても良いのではないか。 - 近似式の適用については、第1章 耐震概要編 p.5に示した通りです。また、補正係数β値は、公表されている文献等を参考にして、本計算例では1.3としています。
- 問1.26
重要な管路のレベル1地震動における検討項目で、地盤の沈下による抜出し量と屈曲角の計算は必要か。 -
地震時の沈下については、地盤の液状化に起因するものであります。従ってレベル1であれ、レベル2であれ、一旦液状化が発生すれば沈下が発生するとの考え方にたったものです。
レベル1とレベル2での沈下量の差異は明確ではありませんので、一律としたものです。採用している沈下率(5%)は兵庫県南部地震の実績値から求められたものであり、厳密にレベル1とレベル2に分けて統計処理したものではありません。したがって、今のところ、一律として計算を行ってください。 -
問1.27
地盤バネ定数の算出において、鉄筋コンクリート管の製品長は、管径によって長さが変更になった場合でも、L=2.43mで固定して考えるのか。 - 製品長なので、φ200~350mmまでは、L=2.0mとしてください。但し部分的な切り管等は管路の全体的な耐震性能を考慮する場合、無視しても問題ありません。
-
問1.28
フレーム計算における法線方向の地盤バネは、プラス側にもマイナス側にも働くものと思いますが、管の全周に地盤バネを考慮した場合、プラスのひずみに関しては、危険側にならないのか。(地盤を押す場合は、地盤バネが働くが、地盤を引張る場合バネは働かないのでは。) -
「指針」の計算例に掲載されているモデルは、引張となる地盤バネをあらかじめ取り除いたモデルとしています。これは、地盤バネは引張には働かないと仮定したことによるものです。このモデルは地震力を直接部材に作用させて行うものであり、かなり安全側の計算といえます。
本計算例では、地中構造物の剛性および空洞を無視して地盤に応答変位を与え、それを静的に地中構造物に作用させる、という応答変位法本来の考え方に立ち返って計算モデルを設定しています。 その際、「地盤と構造物は常に一体となって拳動し、すべりや剥離が生じない」と仮定し、構造物の周囲に地盤と構造物間の相互作用を考えて地盤バネを配置して、これに相対変位を与えることで骨組に生じる応力を求めます。
応答変位法による解析は、地中構造物の変位を主体としてモデル化するのでなく、空洞を無視した地盤の変位を主体としてモデル化しているため、引っ張りバネは解除しない事となります。 -
問1.29
平方向地盤バネ算出時に、表層地盤の変形係数はEo=2800・Nの関係から求めるが、砂質N=45程度であれば、水平方向地盤バネ定数が最大となる。この考え方は正しいか。 -
砂質土でN=49だと、地盤反力係数が最大となるので、地震時水平応力が最大となり、N=50だと応答変位が0なので、地震時応力はかかりません。
これは今のところ、応答変位による耐震計算の不備な点であり、今後の研究課題です。 -
問1.30
管の地盤急変部におけるひずみの計算式は、「ガス導管耐震設計指針」からの引用式になっているが、本来ガス導管指針で用いている設計応答速度スペクトルは、下水道耐震指針のものと異なっており、そのまま用いるのはおかしくないか。
他都市の補完的な耐震指針では、下水道耐震指針の設計応答速度スペクトルに合わせて導いた地盤急変部のひずみ式を用いているケースもある。 - 質問にあるとおり、応答スペクトルが下水指針とガス導管指針で異なるのに対し、κ(カッパ)の値を「ガス導管耐震設計指針」からそのまま用いています。今回の計算例は指針の改定ではなく、指針を補完するものであるため、本文を尊重してそのまま使用しました。なお、ご指摘のような考え方も尊重します。
-
問1.31
設計応答速度の設定について
現在では「グラフによる読み値」になっていますが、この方法で(特に固有周期が小さい場合です)行うと個人差が発生し、計算結果に「バラツキ」が生じると感じる。L1,L2のグラフの式(対数式)の公開は行われないのか。 -
L1、L2のグラフ共、直線間の各節点座標が明示されているので、2点間を結ぶ対数関数の式を設定すれば、TsからSvを数学的に求めることが可能です。ソフトメーカーから市販されている耐震計算ソフトもこの方法で計算を行っているようです。
以下に2点間を結ぶ対数関数式を示します。両対数Ts~Svグラフの各直線を対数関数式 logSv=A・logTs+B (= log10(A・logTs+B)) で表すとすれば、両辺のlogを外し、Svは次式で求められます。
Sv=10(A・logTs+B)
ここに、 Sv;設計応答速度(m/s) Ts;表層地盤の固有周期(s) A,B;地震動レベルと地域別に応じた係数で次の表の値をとります。 <参 考>A,Bの値一覧表 重要度区分 Ts(s)範囲 A B レベル1
A地域Ts<0.25 1.28873 0.0088825 0.25≦Ts<0.5 0.48904 -0.47257 0.5≦Ts Sv=0.24 一定 (同上)
B地域Ts<0.25 1.28671 -0.063956 0.25≦Ts<0.5 0.49252 -0.54211 0.5≦Ts Sv=0.204 一定 (同上)
C地域Ts<0.25 1.28998 -0.14418 0.25≦Ts<0.5 0.48543 -0.62856 0.5≦Ts Sv=0.168 一定 レベル2
A~C地域共通Ts < 0.70 1.18329 0.086385 0.70 ≦ Ts Sv=0.80 一定
ダクタイル鋳鉄管(推進用)については、「日本水道協会;水道施設耐震工法指針・解説,1997年版」の設計応答速度スペクトルに準拠します。ただし、この耐震指針では式を公表していないので、ここでは参考扱いです。設計応答速度Svの単位を下水道に合わせ、[m/s]としているので注意してください。式の展開方法は前述と同じです。A,Bの値一覧表 重要度区分 Ts(s)範囲 A B レベル1 Ts<0.25 1.28873 0.53177 0.25≦Ts<0.5 0.48904 0.050305 0.5≦Ts Sv=0.80 一定 レベル2
(上限側)Ts<0.7 1.29797 0.20106 0.7≦Ts Sv=1.00 一定 レベル2
(下限側)Ts<0.7 1.26251 0.040664 0.7≦Ts Sv=0.70 一定 -
問1.32
表層地盤の固有周期を算出する式(Ts=1.25TG)のうち、安全率1.25に関して、設計地震動レベル1、レベル2共、同じ数値で良いのか。鉄道トンネル等では、レベル2で1.67と異なる数値が用いられているが。 -
レベル1とレベル2では地盤のひずみが異なり、レベル2のひずみが大きいことが知られておりますが、今回の計算例は指針を補完するものであり、現指針でレベル1・レベル2共に1.25を採用しているため、同じ値を使用しています。今後の指針改訂の際は、地震調査データなどを収集し、値の改訂についての検討が必要でしょう。
ちなみに、この1.25とは、地震動により地盤が緩んで強度が低下するため、固有周期が当初地盤の強度で推定するよりも長くなることを意味するもので、安全率ではありません。
-
問1.33
p.2耐震設計マトリックス表の内容について
硬質塩ビ管の管渠と管渠の継手部検討で、推進用の場合、屈曲角、抜出し量共、耐震検討を必要としない項目になっているが、それはなぜか。 - 塩ビ管の場合、基本的には管渠と管渠の継手部の検討は必要です。本計算例では推進用塩ビ管は、接着接合方式であるリブカラー付直管を示しています。この場合、管渠と管渠は接着剤により接合されており、一体として地震の動きに追従するため、管渠と管渠の継手部の検討は行わないこととしました。管の接合状態により検討項目が多少異なるため、注意が必要です。
-
問1.34
粘性土の層で土圧増分が、-16.170になっています。計算上ではそうなるかもしれないが、その値を採用してもよいのか。 - 土圧増分については「-」としますが、鉛直土圧が「-」となった場合は「0」とします。
-
問1.35
開削工法や推進立坑等の埋戻し土で、管廻りが埋戻しされている時の土質設定はどのように考えるのか。周辺地盤と同様と考え、近接した地質調査を採用して良いのか。 - 地震動の影響は、局部的なものではないので、埋戻し土については考慮せず、原地盤の土質で考えます。
-
問1.36
開削部における、鉛直土圧は埋戻し土の単位体積重量を使用しなくて良いのか。 - 原地盤の特性値を採用します。
-
問1.37
液状化判定により、管の周囲を地盤改良やソイルセメント等で埋戻した場合は、地盤バネはどの様に考えるのか。
Eo:表層の変形係数であれば改良等によりN値は原地盤より向上するはず。しかし、地震という規模で考えると改良範囲は微小とも考えられる。 - 地震規模で地盤の定数を考えるので、管の周囲が地盤改良土でも埋戻し土でも、基本的に、周辺地盤の土質定数を使用してください。
-
問1.38
表1-3 永久ひずみに対して基層までの間に改良層がある場合、表層の厚さを補正するのか、しないのか。 - 永久ひずみは阪神大震災の実測から算出したものでありますが、改良土層の有無による違いについては考慮されていません。改良によって非液状化が確立されている場合は、検討の余地はあると思われますが、永久ひずみを防止し得る改良範囲については判断が難しく、改良効果は考慮しないのが安全です。
-
問1.39
常時土圧の考え方は表1-5により、粘性土は土水一体の全土圧としている。一方、現場打ちボックスカルバートのp.8-13水平土圧では土水分離で計算している。
さらに、同項の水平土圧算定表ではZ=5.15mでは粘性土であるのに土水分離で算定している。また、Z=5.15mで用いられている土の水中重量γ‘の設定根拠が不明。
なお、「共同溝設計指針」、「駐車場設計・施工指針 同解説」、「道路土工 ボックスカルバート工指針」では、粘性土についても土水分離で常時土圧を算定し、水中重量は湿潤重量から9KN/m2を差し引いた値を採用していると思います。 - 設計施工時の土圧の考え方と地震時土圧の考え方は異なります。地震時はあくまでも現地盤を対象として土圧を計算します。したがって、粘性土は土水一体の全土圧となります。
-
問1.40
接続部の屈曲角の計算結果について
計算では、1度以下となるが、実際はもっと曲がりが発生すると思う。(本当に0度30秒位の屈曲であるならば、人孔継手部は破壊に到らないと思う。)1度以下の屈曲角の計算結果は適当であると言えるのか。 - 差し込み継手管渠の屈曲角は兵庫県南部地震(1995年)の被災実態について、8,000以上のスパンの実態データ分析に基づき、なるべく簡易に予測できる式にまとめたものです。ですから、屈曲角の計算結果が1度以下となっても、現行指針に従う限り、妥当なものと扱ってください。
-
問1.41
常時のせん断力について
管の常時応力については、指針p.161にある理論解がありますが、計算例の応力分布と一致しない。(ギザギザの分布となっている。)シールドの耐震計算ではせん断力についても照査するので、理論解と異なり、ギザギザの応力分布を採用するのは問題ないか。 -
せん断力がギザギザになっているのは、円環を多節点骨組構造としたモデルを採用し、計算例では節点として計算した結果です。節点を増やしていくと、ギザギザの程度が少なくなり、究極の円形では連続することとなります。今回、計算例で節点を採用しているのは、この施工条件では計算結果としてそれほど過大なせん断力の値となっていないからです。
シールドなどで、管径が大きく、ギザギザの程度が大きくて過大なせん断力となっているような場合は、節点数を36以上とするなどの対応が必要です。 -
問1.42
水平土圧の計算(たとえばp.1-14)はランキンの主働土圧を用いることになっていますが、長年地中に管があることを考えると、静止土圧が作用しているものと考えられます。あえて、ランキンの主働土圧を用いている理由を教えてください。また、ランキンの主働土圧を用いる場合には、粘着力による低減を通常考えますがp.1-14の式に粘着力の低減の項が無い理由を教えてください。 - トンネルに作用する水平土圧に関しては、シールドセグメント設計に用いるように、土質条件、地盤反力係数への期待度、施工条件等を配慮して決定するものでしょう。ヒューム管の様な剛性の高い管路に関して、地盤反力をどの程度見込めるかは議論のあるところです。従って鉄筋コンクリート管に関しては、側方土圧のみを考えることとしました。この際の側方土圧係数は主働土圧から静止土圧係数まで工学的に判断して採用する事としています(計算例1-4 注)参照)従って計算例ではランキン式を採用しておりますが、特にランキン式にこだわるものではありません。
-
問1.43
バネ常数の計算方法について
円形マンホールの側方バネの計算では、マンホールの換算載荷幅を求める時、マンホールが円形であることを考慮して外径を0.8倍していますが、管の場合には管が円形であるにもかかわらず、0.8倍の低減を行っていません。この理由を教えてください。 - 構造モデルの違いによるものです。マンホールは弾性支承上の梁モデルとしておりますが、管は多節点フレームモデルとしております。マンホールのバネは幅全体を換算しているため、丸くなっている部分を考慮して0.8倍としておりますが、管は一つの部材は直線ですので換算しません。
-
問1.44
耐震指針p.55近似計算法における表層地盤の動的ポアソン比の導入公式について教えてください。

において、
・νpの表記はどこにもないのですが。
・νsを求めるのに、式はνsの関数にはならないと思います。 -
この式は「水道施設耐震工法指針・解説」p.21を参照しております。正確な式は次の通りです。
νs={1-2(Vs/Vp)2}/{2-2(Vs/Vp)2}
ここに、νs:動的ポアソン比 Vs:S波のせん弾弾性波速度
Vp:P波のせん弾弾性波速度
Vpの算定式は掲載されておりませんが、動的ポアソン比νsの値は、一般の沖積および洪積地盤では地下水位以浅で0.45、地下水位以深で0.5、軟岩で0.4、硬岩で0.3としてよいです。 -
問1.45
「表1-1 耐震設計マトリックス表」の中で、○印の箇所は省略扱いとなっているが、具体的に引用すべき指針・示方書・設計要領等について - 「表1-1 耐震設計マトリックス表」において○印となっている項目は、他の管種において計算例が示してあり、管の強度や許容値が異なるのみで、計算手法は同じなため省略しております。したがって、同等な管種の計算例を参照してください。管種毎の耐震設計に必要な検討項目と参考文献は表1-4に示してあります。
2. 管の耐震計算
-
問2.1
マンホールと本管接続部の抜出し量及び屈曲角の許容値は、管きょと管きょの継手部の許容値と同一と考えてよいのでしょうか。 -
(i) 管の継手性能でチェックすれば現在の可とう継手で対応可能です。
(ii) 大口径の管きょの場合可とう継手の価格が嵩む場合には人孔と管体の一部を一体化すれば管渠の継手で対応することも可能です。
以上から、第1次的には、管きょの継手性能で検討すれば良いことになります。 -
問2.2
曲線推進部における管きょと管きょの継手部の抜出し量、管体応力の考え方について。 -
1) 抜出し量について
地震時の抜出し量は、曲線施工による初期の目開きを加味します。
(カーブ推進による抜出量)+(地震時抜出量)< 許容値
2) 管体応力について
下水道施設耐震計算例は一般的な布設条件を前提としているため、曲線部等特殊条件のものは別途検討が必要です。 曲線部の管体応力についてはガス導管耐震設計指針(日本ガス協会)が参考になると思いますがこれでは、継ぎ手の効果については全く考慮されておりません。 差込継ぎ手を有する推進管についてはこれの効果を解析することが必要と思われます。 -
問2.3
液状化対策として、塩ビ管の管基礎材料に砕石を用いるべきでしょうか。 -
液状化対策としての砕石基礎は有効な対策として位置づけられていますが、管にかかる荷重状態や施工性、管理者の埋設条件なども考慮して決定する必要があります。
なお、下水道用硬質塩化ビニル管の道路埋設指針には、「基礎材に含まれるれきの最大粒径は、20mm以下とする」と記載されています。 -
問2.4
鉄筋コンクリート管における固定支承、立坑空伏せ部の計算はどのように行うのでしょうか。 -
鉄筋コンクリート管は継手間隔が極めて短く、屈曲性、伸縮性に豊むことから耐震性能に優れた管材と考えられています。従って、継手性能を損なう固定支承をできる限り使用しないのが良策です。布設条件、施工条件から固定支承を採用する場合は、基礎形状等を考慮する必要もあります。
立坑空伏せ部のように360°固定の場合には、鉄筋コンクリート構造として解析するのも手法の1つと思われます。
一方、地震時は基礎が破壊されるので、拳動は自由支承に近いとの意見もあり、今後、検討を重ねる必要がありますが、基本は継手性能を損なわないことが良策です。 -
問2.5
推進工法において可とう管は必要なのでしょうか。また、必要な場合設置位置はどこにすればよいのでしょうか。 -
人孔部及び立坑坑口部の両方に可とう継手または可とう管を設置するのが理想的ですが、立坑坑口部のみでも可能です。
マンホールと本管接続部は人孔と空伏せ部の地震による挙動が異なり、また、立坑と本管接続部は空伏せ部と管路部の挙動が異なるためです。
ただし、構造上、どちらか1箇所のみに設置する場合は、同じ立坑基礎上に築造される人孔と空伏せ部は地震時に一体的に挙動すると考えれば、立坑と本管接続部に設置するのが良いでしょう。 -
問2.6
抜出し量の検討において、地震動による抜出し量と永久ひずみによる抜出し量、地盤急変部による抜出し量を計算し、その合計を抜出し量とするのでしょうか。また、検討位置は管の中心でよいのでしょうか。 -
抜出し量照査は、それぞれ単独の計算値の合計値ではなく、各計算値の最大値を許容値と比較して照査を行います。
地震の永久ひずみによる抜出し量を計算する際の、永久ひずみ1.5%は神戸の地震の状況から調査されたものであるので、これは地震動も含めた値であると考えてよいものと思います。
また、地盤急変部での抜出し量の計算においても「下水道施設の耐震対策指針と解説」p.53に示されている様に、εG2 = √εG12 +√εG32となっており、これは、地震動と急変部を合わせて考えていることになります。
抜出し量の検討位置は、管中心としています。 -
問2.7
マンホールと本管の接続部の計算において、マンホールから抜出し量及び屈曲角の計算を行う継手部までの距離(マンホールから1本目の管きょの長さ)は決められているのでしょうか。 - マンホールから1本目の管は、耐震対策上半管以下とする必要がありますので、必然的に半管以下の長さとなります。ただし、可とうマンホール継手を使用する場合はこの限りではありません。
-
問2.8
剛性管の継手性能の計算では、継手部の変位量(又は変位角)と継手の許容値で行うこととなっていますが、軸方向圧縮に関する照査(応力照査等)の考え方を教えて下さい。また、軸方向圧縮と曲げは合計(荷重・応力レベルで)されると考えられますがいかかでしょうか。 -
指針で考慮しておりませんので、本計算例でも考慮しておりません。
管軸方向の研究は未だ十分ではなく、今後の課題といえるでしょう。 -
問2.9
ダクタイル鋳鉄管の管体応力の計算では自動車荷重を考慮していますが、その他の管種では考慮しなくてよいのでしょうか。また、ダクタイル鋳鉄管の許容値がメーカーによって異なっているようですがどの値を使用すればよいのでしょうか。 -
本計算例では、原則として自動車荷重を考慮しないこととしました。しかし、ダクタイル鋳鉄管の圧送管だけは、水道施設耐震工法指針に準じているため、自動車荷重を考慮しています。
許容値については、下水道協会規格G-1、G-2に定めがあります。
その他の管はその管を製造するメーカー及び協会などにお問い合わせください。 -
問2.10
推進工法において1スパンに複数のボーリングデータがある場合、1スパン同一の管種を使用するか、その位置で管種を区別すべきでしょうか。 -
1スパンに複数のボーリングがあり、そのデータが大きく異なっている場合は、それぞれの設計条件で耐震計算を行う必要があり、計算結果として管種が異なる場合は異なる管種を使用することが必要です。
これは、1スパン内で50N管と70N管の推進管を使い分ける必要があることと同様の理由です。どこで使い分けるかは、責任技術者の判断となります。
3. 液状化関連
-
問3.1
設計地震動(レベル1、2地震動)と設計水平震度(タイプ I 、II 地震動)との関連性について。 -
タイプ I 、II 地震動の概念は、道路橋示方書の保有水平耐力法で使用している水平震度で、レベル1、2地震動との数値的な関連性はありません。従来の共同溝耐震設計の考え方をレベル1地震動、関東大震災クラスの地震をタイプ I 地震動、兵庫県南部地震クラスをレベル2地震動またはタイプ II 地震動としています。
地震の原因を地質学的に解説すると、2つに分けられ、1つ目は地殻プレート同士がこすれあって起こる「プレート境界型地震」、2つ目は地殻プレートそのものが破壊して起こる「プレート内地震」です。道路橋示方書のタイプ I 、II 地震動は、これらを区別しているが、どちらもレベル2地震動相当です。
-
問3.2
液状化判定は、レベル1及びレベル2の両方を行うのですか。 - 液状化の判定は、レベル1,レベル2とも行って下さい。
-
問3.3
液状化の計算におけるγi1、γi2、γ’i2の考え方について。 - 液状化の計算における各定数の考え方は、道路橋示方書又は共同溝設計指針に基づいています。全上載圧に対して有効上載圧は浮力を引いた荷重と考えられます。本計算例では、γ’i2=γi2-10としています。
-
問3.4
液状化地盤がある場合の土質定数の低減や液状化部分のバネ定数の考え方について。 - 地盤バネ値の推定に用いる割増係数αは、地震時も常時と同じ値α=1として、結果的に地盤の土質定数を低減しています。したがって、それ以上の土質定数の低減は考えないで、現地盤の設計定数を用いることとしています。
-
問3.5
レベル2地震動時の沈下率は5%ですが、レベル1地震動時は何%ですか。 -
地震時の沈下は、地盤の液状化に起因するものです。従ってレベル1地震動であれ、レベル2地震動であれ一旦液状化が発生すれば、沈下が発生すると考えられます。レベル1地震動とレベル2地震動での沈下量の差異は明確ではありませんので、一律としたもので、レベル1地震動時も5%です。
-
問3.6
永久ひずみを考慮する条件はどのようなものでしょうか。 -
管の埋設位置の地盤が液状化する場合に永久ひずみを考慮します。管の埋設地盤が非液状化層の場合でも、管の下部層が液状化を起こす場合、沈下による検討をする必要があります。
指針では、永久ひずみを考慮するケースとして、以下の場面を提示しています。
[1] 護岸の移動等に起因する液状化地盤
[2] 人工改変地の傾斜地盤
[1]については、「設計地震動に対して護岸の推定移動量が50cm程度未満であることが、他の方法により確認される場合には、本項で定める地盤の永久ひずみ(引張り)及び地盤変位を考慮する必要はない。」と解説しています。
以上より、[1]、[2]に該当しない地盤、及び側方流動が発生するとしても推定移動量が50cm程度未満である地盤においては、永久ひずみによる変位を考慮しなくて良いということになります。
なお、液状化の恐れがなくとも[2]に該当する地盤においては逆に、永久ひずみによる変位を考慮することになります。
永久歪みは、護岸線から100m以内が1.5%、護岸線から100m以上が1.2%と定められています。これは、兵庫県南部地震と新潟地震におけるデータを整理して、80%の非超過確率として定めてもので、100m以上の場合のデータは数百mまでのデータを解析したものです。したがって、数百m以上離れたところは考慮する必要はありません。数百mとは、一般的には4~500mです。 -
問3.7
埋設管が液状化する層のどの位置に埋設されているか、による考え方について。 -
液状化する層の境界面に管が設置される場合は、危険側に全部液状化すると考えて計算すれば良いと思います。
液状化層が埋設管の下にある場合は、沈下のチェックが必要ですが上にある場合は必要ありません。管が埋設されている層より深い層で液状化する層厚を累加し5%を乗じます。管が液状化層内の場合は、管頂から液状化層の下端までの厚さを液状化層厚と考えます -
問3.8
液状化によるマンホールの沈下は考慮しないか。 - 管渠と管渠の継手の検討が目的であるので、人孔は沈下しないとするのが安全側の考えです。人孔間隔が極めて短い場合は、前後の人孔まで加味して計算するような手法も考えられます。
-
問3.9
液状化における過剰間隙水圧について。 - 共同溝指針では、過剰間ゲキ水圧を考慮していますが、本計算例では水道耐震指針に基づいて計算を行っていますので、過剰間ゲキ水圧は考慮しておりません。
-
問3.10
液状化による浮力について
[1] 安全率の考え方
[2] ごく軟弱なシルト層や粘性土層の浮力の考え方
[3] 浮力に対する抵抗力の考え方 -
[1]について
水道耐震指針の外に共同溝指針、駐車場指針等に提言されているところですが、浮力の考え方、抵抗力の考え方にも差異があります。本計算例は水道耐震指針に準じておりますので、安全率Fsa≧1.0としております。
[2]について
現地盤から3m以内で軟弱層と判定されたシルト層や軟弱粘性土層(一軸圧縮強度0.02N/mm2以下)は、必ずしも非液状化層とは言えず、浮力の検討は必要でしょう。
[3]について
共同溝設計指針のように上載土の重量を考慮する考え方もありますが、今回の計算例では非液状化層のせん断抵抗を考慮する水道耐震指針の考え方に基づき計算を行っています。 -
問3.11
液状化対策の必要性について。 -
指針に示されているように、地盤改良、置換工法等の液状化層を非液状化層とする方法、過剰間隙水圧を逸散させ液状化を軽減するための方法、あるいは管の浮上がり防止のために重量化する方法等があります。ただし、液状化する全ての管路網に対して対策を行うことは費用対効果の面で難しいのが実状です。
周辺地盤の状況も合わせて対策を検討するのが良いと思われます。
4. 計算モデル
-
問4.1
鉛直断面計算における常時荷重として、管内水重量、管自重、活荷重を考慮しない理由を教えて下さい。また、ダクタイル鋳鉄管の圧送管は自動車荷重を考慮しておりますがその違いを教えてください。 -
鉛直断面計算においては、管内水重量・管自重・活荷重とも、水平土圧、地震時増分荷重によって生じる曲げモーメントを相殺する方向に働く傾向にあり、また「指針」巻末の計算例においても考慮されていない為、本計算例でも考慮しておりません。今後の検討課題と思います。
しかし、ダクタイル鋳鉄管(圧送管)は、上水道への実績が多いことから、「水道施設耐震工法指針・解説」に準拠しておりますので、管軸方向の照査が対象となり、常時荷重として内圧と自動車荷重を考慮しました。
-
問4.2
常時土圧(静止状態の土圧)による断面力に地震時(応答変位による土が変形した状態)の断面力を加算して断面力計算を行ってよいのですか。 -
応答変位法は地震時に地盤に生じる変位、変形、地盤内応力を計算し、これを地下構造物に静的に作用させ、変位、変形、断面力、応力度を計算する手法であり、地震力を適切に評価し、地震時増分断面力を計算すれば、常時断面力+地震時増分断面力で計算しても問題ありません。
-
問4.3
管の鉛直断面計算でフレーム計算と近似式による計算結果を比較した場合、近似式で計算した値がフレーム計算した場合の数倍の値が出る場合があるという記述がありますが、本来、近似式は一様地盤中のリングモデルの理論解を簡単にしたもので、土木研究所資料「大規模地下構造物の耐震設計法ガイドライン(案)」では近似式と動的解析の結果が比較してあり、よく値が一致しています。このことから、フレームモデルと近似式で同じ単層地盤で計算すると同じような答えが出ないとおかしくないでしょうか。 -
本計算例の解析モデルと近似式による計算結果の差は、
[1] 地盤バネの考え方が異なる。
[2] 近似法は理論解から発展しているので、周面せん断力が考慮されている。等がその要因と思われます。 -
問4.4
フレーム計算モデルにおいて、地盤変位は単層地盤として計算していますが、管の周囲に配置する地盤バネは管のある位置の地盤のN値から計算しています。地盤変位を単層地盤と算定している以上、地盤バネも単層地盤としたバネを用いるべきではないでしょうか。 地盤が単層地盤とみなせない場合には鉄道総合研究所「鉄道構造物等設計標準・同解説耐震設計」にあるようなB・C地盤のモデル化を採用したほうがよいと思います。 - 応答変位量は地盤一様として求めているので単層地盤としてバネを求めるのが理論的ですが、Ts、土質状況を含め一様地盤に換算する手法がないので、やむを得なく地盤バネは管のある位置の地盤から計算しています。鉄道総合研究所の事例等の考え方は尊重できるので、それに準じるのもよいと思います。
-
問4.5
既設管の耐震診断において、近似式による応力度チェックを行ってよいでしょうか。膨大な「重要な幹線等」の既設管があり、これら全てについてフレーム計算を行うと大変な作業量となる。 -
耐震診断については、本計算例では触れていませんが、基本的な考え方は本計算例を参考にして下さい。
耐震診断の方法として、全域、全線を総括的に一度に診断する場合は、一次診断として近似式で計算して許容値を満足しないスパンを抽出し、二次診断としてフレーム計算による、等の方法もあります。
-
問4.6
常時断面のフレームモデルの場合、ピン支点と水平ローラー支点を設けていますが、どのような理由からですか。又、地震時増分断面のフレームモデルの場合は同じような支点は設けないのですか。 - 常時荷重の場合には、フレームソフトにより支点を設けないと計算できない場合があるので、ボックスカルバート等の支点条件の考え方に準じて設けました。なお、地震時増分のモデルは、法線方向と接線方向のバネで支えますので、支点は必要ありません。
-
問4.7
安全係数をすべて1.0と押している根拠は何か。 -
本計算例では、塑性域におけるコンクリートの靭性を考慮していないので、安全係数を1.0としています。
管路施設の耐震設計では弾性域による計算を採用しています。また、コンクリート標準示方書では弾性域を越えて塑性域においても構造に靭性があるとして、発生応力の低減を考慮しています。 -
問4.8
各管種の許容安全率にバラツキがありますが、許容安全率の考え方を教えて下さい。 -
短期荷重であり、各許容値を超えないことが条件であることを考えれば安全率は1.0でよいと思います。
ただし、ダクタイル鋳鉄管(圧送管)においては、「水道施設耐震対策工法指針・解説」を準用しており、下水道用ダクタイル鋳鉄管(G-1)で、管厚計算、許容曲げ角度、抜出し量等の安全率を2.0以上としていることから、計算例においても同様にしました。 -
問4.9
両側載荷モデルの場合に、支点を設けないで計算ができるでしょうか。 - 地震時増分荷重に対しては、管を全周バネにより支承しておりますので、一般のフレームソフトで計算できます。
-
問4.10
常時断面におけるフレームモデルの基礎支承角の差異は考慮する必要はないか。 - 耐震計算では管渠の布設後の安定状態を対象とし、管と周辺地盤が一体化したものと考えています。従って、布設時の支承角は考慮しなくてもよいと思います。
-
問4.11
従来の下水道協会式において考慮していた、シートパイル引抜き時の付加的土圧は耐震計算では、どのように解釈すればよいか。 - シートパイル引抜き時の付加的土圧は施工時のものです。耐震設計に採用する常時の土圧は施工完了後の埋め戻し土が安定した状態を想定していますので、考慮する必要はありません。
5. 計算例以外の耐震計算手法
-
問5.1
推進工法で施工する場合等における、以下の事例に対する継手部の屈曲角や抜出し量等をどの様に判断すればよいか。
[1]ヒューム管の空伏せ(360°巻立)部について
[2]塩ビ管で砂付マンホール継手を使う場合について
[3]FRPM管を防護コンクリートで巻き立て、人孔と一体とした場合について -
推進工の立坑部では、人孔接続部と立坑坑口部の両方に可とうマンホール継手または可とう管、切管を設置するのが理想的ですが、立坑坑口部のみでも可能です。
[1]について
人孔と空伏せ部は基礎を共有しており、一体的に挙動すると考えられます。そのため、立坑坑口部のみ、可とう管または切管を配置してください。可とう管はその許容値で判断し、切管は管の継手性能で判断します。
[2]について
人孔と砂付短管は一体的に挙動すると考え、管の継手性能で判断します。
[3]について
[1]と同様、人孔と巻立部は一体的に挙動するので、切管を配置し、その継手性能で判断します。
-
問5.2
サヤ管方式にて鋼管を推進して,その中へ本管(塩ビ管等)を挿入し,セメント系充填材に固定する場合の耐震計算はどのように考え,どの管体の式を用いればよいかについて。この場合,鋼管の接続は全周アーク溶接にて接続するものとし,可とう性が期待できないものとします。
また,この場合の有効長Lはどうなるのか,並びにサヤ管(鋼管)に強度があるため,鋼管のみ耐震計算として考えてよいかについて。 -
鋼管は本設扱いとし,水道施設耐震工法指針・解説の一体構造管路・鋼管の場合を参考に計算してください。
モルタル充填した場合,管体ひずみに安全側に働くと考えられる為,鋼管の計算で安全を照査すればよいと思います。
鋼管の場合,管軸方向の管体ひずみで照査するので有効長は計算上関係ないことになります。
なお,マンホールと本管の接続部は,可とう性を有する継手構造を検討する必要があると思います。例えば立坑内は塩ビ管のみとし,鋼管とマンホール接続部には継手部を設けて可とう性を持たせるという考え方もあります。
-
問5.3
都市下水路などの開渠の計算方法は,どのように耐震計算するのか。 -
横断方向の耐震計算の方法として,以下の二通りの方法が考えられます。
[1] 頂版部材の無いボックスカルバートと考えて本計算例を準用する。
[2] 処理場などの施設構造物と同様に震度法で計算する。
縦断方向計算についても,状況に応じて,本計算例を準用してください。 -
問5.4
レベル1の場合において,本体,継手部については安全であるが,液状化による地盤の浮上がりまたは沈下によって流下能力が確保できないとすると,どういう対策を講ずれば良いか? -
浮き上がりや沈下を防止するための液状化対策として指針に次のような記述があります。「レベル1地震動に対して,液状化時に発生する過剰間隙水圧を速やかに消散させ,管きょ底面に作用する揚圧力の低減が期待できる埋戻し材(砕石等)を用いる。」これを参考に検討すればよいと思います。ただし,砕石を使用する場合,管材により、粒径に注意する必要があります。
-
問5.5
マンホールまたは管路の途中より基盤層となる場合,あるいはスパンの一部が基盤層に入るような場合、耐震計算は必要なのか?必要とするなら,どのようにモデル化すべきなのかについて。 -
マンホール,管路が途中より基盤層に入っている場合,ケースバイケースで対応するしか今のところありません。基盤層部分を固定と考えるか,ヒンジと考えるかは責任技術者の判断となります。
管路が完全に基盤層に入っている場合、応答変位法の趣旨から判断し,岩盤部でも相対変位があると仮定することは無理があると考え,基盤層内では耐震計算は実施しないことが合理的であるとの結論に至っております。
-
問5.6
マンホールやBoxの支持力計算はこれまでと同様に,道路橋示方書に準じて考えるものと判断して構わないかについて。 - ご指摘の通り、道路橋示方書等に準じます。
-
問5.7
水管橋,橋梁添架の耐震設計方法について。 - 水道施設耐震工法指針・解説の水管橋及び添架管の項を参照してください。
-
問5.8
圧送管の管種について,K形・T形があるがどちらを採用すべきかについて - 継手構造が異なるだけで,性能はほぼ同じです。経済性・施工性(直配管)はT形が優れているが,曲げ配管が多い場合はK形の施工性が優れています。そのような点を参考にされ,管種を設定してください。
-
問5.9
内形が円形状で外形が円形でない埋設管の耐震計算方法について。 -
横断面の強度検討に際しては,フレーム計算によるのが原則です。円形のハンチを考慮したBox等のフレーム形状としてモデル化することが考えられます。
継手の許容値に関しては,実験等を含めて求める必要がありますが,継手部の拳動の計算については,差し込み円形管に準じても良いのではないかと考えられます。なお,ボックスカルバートの計算例では,P.Cで緊結して可とうBoxで対応しています。 -
問5.10
圧送管等で,塩ビ管で離脱防止金具,ダク管なら特押などを使用する場合の抜け出し量等の計算方法について。 -
塩ビ管に離脱防止金具を使用する場合は,作用する力が離脱阻止力を上回ると,離脱金具が離脱しますので,チェックして下さい。
ダクタイル管では一般用(K形,T形,U形等)で計算し,液状化の可能性があり,大きな地盤変状がある場合には,鎖構造の耐震継手管(NS形,SⅡ形,S形等)及び離脱防止用(KF形,UF形等)管等の採用を検討する必要があります。特押は耐震設計が必要なところでは使用しないで下さい
-
問5.11
圧送管に塩ビ管を使用したい場合,計算基準は「水道施設耐震工法指針・解説」に準拠してよいかについて。 -
塩ビ圧送管の場合は,基本的に水道施設耐震工法指針・解説により計算を行うこととします。
また、塩化ビニル管継手協会より,上記指針に基づいて作成された水道用硬質塩化ビニル管の耐震対策についての資料が発行されており,これを参考にするものよいと思います。 -
問5.12
塩ビ推進に使用する塩ビ継手には接着とゴム輪があるが,接着継手による人孔到達にした場合,レベル2照査の屈曲角の解消法はどうするのか。また,側方流動による継手部の抜け出し量を満足するにはどのような製品を使うのかについて。 -
推進工法用塩ビ管で、差込型の材料を選定してください。なお、マンホール継手で対応できる製品等については塩化ビニル管・継手協会に問い合わせてください。
側方流動についても同様です。 -
問5.13
計算例に記載の無い材料の適用方法について。 - 本計算例では,計算例にある材料以外の材料の使用を否定するものではありません。計算例にある管種と同等と考えられる材料については,その計算手法(本計算例より)を適用するものとします。異なる材料については別途,水道指針やガス導管指針等を参考にしてください。
-
問5.14
本管と取付管接合に関してはどの様に考えればよいかについて。 -
今回の計算例には示していませんが,指針には構造等が紹介されています。また,塩ビ管では取付管に伸縮継手を用いる方法があり,参考にしてください。
-
問5.15
沈埋工法で管を埋設した場合の耐震計算は,耐震計算例にあります通常の計算でよろしいのかについて。 (沈埋工事専門会社に問い合わせしたところ,沈埋工法で埋設した管路は全て一体化しており,特に耐震対策は必要ないとの回答があるが。) -
沈埋工法による場合でも,耐震計算は必要です。
本計算例にある類似モデルでの耐震計算を行うこととしてください。
なお、耐震対策が必要ないとの見解については、その内容を検討のうえ、技術的に安全であると判断できればその限りではありません。
6. 可とう継手関連
-
問6.1
表3-15に掲載されている可とうマンホール継手の選定条件について - 「下水道新技術推進機構」や「日本下水道事業団」などの公的な審査証明を受けた材料のみを掲載していますが、特にこれだけに限定しているわけではありません。 表に掲載されていない製品を使用する場合の許容値などについては、メーカーなどにお問い合わせください。
-
問6.2
接着接合の塩ビ管において、本管と組立マンホールの接合部構造は可とうマンホール継手が必要か? - 液状化する層に埋設されている管を接着接合でマンホールに接合する場合は可とうマンホール継手が必要です。液状化しない場合は砂付短管を使用し、ゴム輪接合とすることも可能です。
-
問6.3
空伏せ工と人孔接続部への可とうマンホール継手の必要性につい - 理想的には、人孔接続部に可とうマンホール継手(空伏せ工と人孔接続部は縁切り必要)、立坑接続部に可とう管を設置するのが良いと思われます。 しかしながら、実際には立坑基礎上に人孔と空伏せ工が一体的にあり、縁切りは難しいため、人孔と空伏せ工は一体的に挙動すると考えて、立坑接続部の出来るだけ近傍に可とう管を配置するか、管の継手が来るように切管を配置すれば良いでしょう。切管配置の場合、管と管の継手性能で本管とマンホールの抜出しをチェックすればよいこととなります。
-
問6.4
副管と人孔接続部への可とうマンホール継手の必要性について - 耐震性を求めるならば、内副管タイプにして本管に可とうマンホール継手を設置することとなります。 外副管の場合は、マンホールと防護コンクリートが一体化して挙動するように、副管部の直上流部に本管継手を設けてください。
-
問6.5
ケーシング立坑やライナープレートを外型枠に現場打ち人孔を築造するような場合の、可とうマンホール継手設置方法について - 立坑接続部(この場合は人孔接続部と同じ)に可とうマンホール継手を設置することとしますが、構造上設置が出来ない場合、切管により調整するか、又は可とうヒューム管のような管材を使用する方法があります。
-
問6.6
人孔と本管接続部の抜出し量が少ない場合の可とうマンホール継手の必要性について - 管と管の継手の許容値以内であれば、マンホール短管を使用することが可能です。但し、管の継手では圧縮側の対応に問題があるので、小口径であれば可とう継手を使用するのが良いと思われます。
-
問6.7
PC・RCボックスカルバートの計算例にそれぞれ可とう性継手が掲載されております。これらの製品には、特許があるのでしょうか。また、これらの製品以外は使用できないのでしょうか。 -
ボックスカルバートに用いる可とう性継手の製品には、特許があります。従いまして、採用に当たっては、その旨にご注意ください。
また、本計算例に掲載した製品は、計算例を示すために取り上げた一例ですので、他の製品も使用できます。
いずれにしましても、可とう性継手につきましては、技術革新により新しい製品が開発されておりますので、選定に当たっては、複数の製品を対象とした耐震性、施工性及び経済性などを総合的に検討のうえ行ってください。
7. ボックスカルバート
-
問7.1
設計水平震度について
[1] p.10-9のレベル1(表3-3)とp.10-10の(表3-5)の違い及び使い分け
[2] p.10-9のレベル2(表3-4)とp.10-10の(表3-6)の違い及び使い分け
[3] p.10-10上段のKhの算定式と下段のKhc1の使い分け -
[1]について
p.10-9レベル1(表3-3)は躯体の慣性力を算出するための地表面の設計水平震度です。(下水耐震指針p.18記述)
p.10-10レベル1(表3-5)は地盤の液状化照査に用います。液状化の判定は道路橋に準じますがL1時の記述がないため、下水道協会「下水耐震指針」に準拠します。(下水耐震指針p.20記述)
[2]について
p.10-9レベル2(表3-4)は躯体の慣性力を算出する為の地表面の設計水平震度です。(下水協指針p.98/第3章,処理場・ポンプ場施設)
p.10-10レベル2(表3-6)は地盤の液状化照査に用います。(下水協指針p.20及び道路橋示方書より)
[3]について
上段のKhは液状化判定用、下段はKhc1は躯体慣性力用に用います。
-
問7.2
「地震時振幅荷重時」とは、どのような時に使うのか。 - 「地震時振幅荷重時」とは耐震設計上の地表面の設計水平震度を設定しています。これに基づき、深さZを用いて照査位置での設計水平深度の低減を図ります。
-
問7.3
Box計算の時は、地震力を片側のみ考慮し、円形の場合はなぜ両側考慮するのか。 - ボックスカルバートも円形管同様、両側載荷にて照査を行っています。現場打ちBoxには詳細な図がありませんので計算例p.9-30、及び下水協耐震指針p.196を参照してください。
-
問7.4
頂版部の周面せん断バネを考慮しない場合と、する場合の明確な基準(Box)は無いのでしょうか?たとえば土被りで判断するならば何m以上でしょうか? - 頂版部の周面せん断バネを考慮する土被り範囲については、明確な規定はありませんので、責任技術者の判断によります。
-
問7.5
Boxの基礎地盤が基盤層(岩盤)の場合では、Boxに作用する地震時土圧、地震時周面せん断力の低減はできないのですか?(実際の地盤では基礎地盤の種類(岩、軟弱地盤等)により、構造物の破壊状況も変化すると思いますが?) - 基盤層の上にボックスが布設されている場合は、地震時土圧は考慮する必要がありますが、底版の周面せん断力は応答変位が0となるので、無視できます。ボックスの途中に基盤層がある場合はケースバイケースで責任技術者の判断で適切なモデル化を行ってください。その場合、基盤層部分の周面せん断力は無視して考えることが出来ます。
-
問7.6
現場打ちBoxにおいて、p.8-33に常時のRC断面算定表があるが、せん断応力度の照査の許容値は偶角部(端部)を考慮して割増係数を乗じなくてよいか?せん断応力度の照査位置は端部(割増係数2)と2dの位置でよいか?
現場打ちマンホール(矩形)の壁を水平ラーメンで解析するときも、せん断応力照査位置は端部と2dの位置で、許容値は各割増係数を乗じてよいか? -
計算例p.8-33の計算表は、「土木構造物設計マニュアル(案)に係わる設計・施工の手引き(案)〔ボックスカルバート・擁壁編〕平成11年11月建設省」(又は、カルバート工指針)に100%準拠した計算表ではなく、原理面に留意し「平成8年制定コンクリート標準示方書;設計編」に準拠した計算式を用いております。
例えば、前者と後者(示方書)とでは、せん断応力算出式に相違があります。
・前者:せん断応力τ=S/(b・d)< S:せん断力,b:部材幅,d:有効高>
・後者:せん断応力τ=S/(b・z)< S:せん断力,b:部材幅,
z:圧縮部と引張部との重心点間距離>
そうした中で、発生応力度が2d位置又はハンチ終端部において許容応力度(せん断は0.39N/mm2)以内に納まっていることを、裏の計算(計算例としての分量を考慮し割愛)で行っていた為、敢えて「土木構造物設計マニュアル(案)」p.80以降の計算例に示されているような、偶角部における許容応力度割増を行う表現までは行わなかった次第です。(計算表上は、偶角部の許容応力度割増を行わなくともOKの判定です。)
ご質問にありますように、現場打ちマンホールも含めて「土木構造物設計マニュアル(案)」に100%準拠される場合でしたら、以下の対応要領となります。
① 偶角部の応力照査位置:偶角部(構造計算上の節点位置)及び2d位置
② 偶角部許容せん断応力度:0.78N/mm2への割増可(同マニュアルp.90)
なお、「土木構造物設計マニュアル(案)」適用に当たっては、これに対応する工事費積算歩掛りとセットでの適用が前提と考えられます点は、説明会でも申し上げてきました。
これは、同マニュアルが、冒頭部に記されている通り、人工手間の削減を目的としていますので、設計だけ本書に準拠して、積算歩掛りを従来通りとすると過大設計となります。この点は、注意が必要です。 -
問7.7
ボックスカルバートの曲線部では斜切製品をボルト連結すると思われますが、その部分の耐震検討をする場合、直線部でのPC鋼棒で連結されている計算例に対応させるにはどう考えるべきですか。 - 曲線部に斜切製品を使用する場合のボルト連結部の耐震検討方法は、今のところ、通常の直線区間と仮定し計算した地震時発生引張り力を斜切部の連結ボルトに作用させて、それに見合うようなボルトの本数と規格を決定すれば良いと思います。
-
問7.8
斜形Box連結で、締固めと同様の効果を出すには、どうしたらいいのでしょうか?ボルトのトルク管理等必要なのでしょうか? - 高力ボルトにより、トルク管理を行いPC鋼材と同様の軸力を導入する事になります。
-
問7.9
地盤反力係数を算出する際、p.10-19にある様にBh=√Av,Av=D×Bの式において、載荷幅の奥行を製品長として計算しているが、p.10-51の様に縦連結を行った場合には奥行の考え方としては、縦連結をした長さ、即ち、可とうの継手スパン50.0mとして考えればよいのでしょうか。あるいは現場打ボックスの場合と同様に、奥行を10mとして考えるべきなのか。 -
本計算例では、連結したボックスカルバートやシールドについては、「日本道路協会;道路土工仮設構造物工指針」の山留工の計算に用いる基準長さを準用して、設計実務上の観点でB=10mとしました。
例として、シールドでは、1スパンが完全連結です。管の奥行長Bとは、地盤バネの値を算出する際に必要な諸元で、Bが大きいほど地盤バネ値は低下します。この時のBの大きさは、単位奥行長1mとする案、平板載荷試験における載荷円板の直径分とする案、地震時に管軸方向に一体で挙動する範囲とする案などを検討しました。また,地盤の管軸方向への変化や、半波長の長さよりも連結区間長が長い場合に果たして一体として挙動し得るのか等も考え,本計算例では実務上10mを採用しました。 -
問7.10
Boxの縦締めは一般に管内より行うイメージがありますが、□600~□700クラスの比較的小さいBoxの場合の縦締め方法は管の外から締めるのですか?対応できる製品の有無を含めて教えて下さい。 - 製作メーカによりサイズは異なりますが、比較的小さいボックス断面は、外側から縦締めを行う様になっています。なお、対応できる製品の詳細についてはメーカーにお問い合わせください。
-
問7.11
既製ボックスカルバートの計算において、1スパンを何故50mと仮定したのか。50m以下の現場が非常に多い、この様な場合は可とう部は必要ないのか。 -
1スパン長50mは可とう性ボックスカルバート協会から出されている設計例を引用しました。実際の計算上の根拠付けとしては、地盤振動の波長Lの1/2以内を目安にする考え方もあります。しかし良い地盤条件では、波長がL=30m程度に算出される場合もあるため、ケースバイケースでの責任技術者の判断となります。
1スパン内で継手部の耐震計算を行った結果OKであれば、あえて可とう性継手を設置する必要はありません。本計算例の縦方向の耐震設計計算は、両端がフリーの場合の構造モデルですので、両端が固定されている場合については、短いスパン長(20m程度)においても両端に可とう性継手が必要となる場合があります。
尚、本計算例に記載した既製ボックスカルバートは、製品間をPC鋼材にて縦締め緊結されたモデルに対して耐震計算事例を示したものであり、異なる連結方法を用いた既製ボックスカルバートを採用した場合は、根本的な耐震設計理論が異なるためこの限りではありません。 -
問7.12
慣性力について指針においては、矩形きょについて、上ハンチの慣性力を見込んでいるが、本計算例では見込まれていない。ハンチについて慣性力は考慮しなくてよいのか? - 本計算例では影響が小さいと判断して省略しましたが、省略できる範囲は明確でない事から、指針巻末の計算例にしたがって、ハンチの慣性力を考慮する方法もあります。
-
問7.13
初歩的な質問ですが、ボックスカルバートの計算にあたり、通常の構造計算のほかに、必ず耐震計算も行わなければいけないのですか? -
「重要な幹線等」であれば、必ず耐震設計を行います。
「その他の管路」では、「軸方向の伸縮量算出とEXP.J仕様設定」を計算します。(計算例p.18参照)
-
問7.14
表1-1耐震設計マトリックス表における“耐震検討を必要としない項目”についての確認
[1] マンホールとの接続部では検討不要とありますが、ボックスカルバートとポンプ場等の施設構造物との接続のように挙動が違うものは“検討必要”と思われますが如何でしょうか?
[2] 現場打ちで屈曲角検討不要の理由は?
[3] プレキャストボックスカルバートにおいて永久歪による抜け出し量及び地盤急変部での抜け出し量に対する検討を不要とした理由は?
[4] 液状化による地盤の沈下に対する検討を不要としたい理由は? -
[1]について
挙動が異なるボックスカルバートと施設構造物の接続部では検討は必要です。本計算例では、特殊マンホールではなく、マンホールとボックスカルバートが同一断面の計算モデルを採用しているため、「検討不要」としました。
[2]について
「検討は必要」ですが、実状は計算値が小さいため省略しています。
[3]について本計算例ではPC鋼材による縦締め緊結継手を用いておりますので「検討不要」としました。差し込み継手を用いた場合は、抜け出し量の検討は必要です。ただし、この場合の許容値などはボックスカルバート製作協会にお問い合わせください。
[4]および[3]について
本計算例は直接基礎のボックスカルバートを前提として耐震計算を行っています。ボックスカルバートのような一体化した構造物の液状化時の挙動については、研究途上の分野であり、未定の部分が多いため、実務上、本計算例では考慮しておりません。 -
問7.15
10.プレキャストボックスカルバート(RC)p.10-72下より2行目について
∴ P′= 6,443kN ≧ Pe = 400kN
すなわち地震時において目地は離間すると見なす。とありますが、地震時に発生するボックス函体に作用する軸方向引張力(P′)は、PC鋼材の有効緊張力(Pe)よりはるかに大きく、事例では、PC鋼材の破断荷重(1700kN)をも超えた軸力が作用している結果とはならないのでしょうか。 -
既製ボックスカルバートの継手構造については各々の既製ボックスカルバート協会毎に工夫されており、本計算例では、その一例として各ボックスカルバートを縦締めPC鋼材にて接合された部材の継手部における耐震計算手法を紹介しました。
この計算手法は「プレキャストコンクリート共同溝設計・施工要領(案)」の考え方に基づいており、計算手順の第1段階として目地部の離間の確認を行います。御質問の通り計算値だけで判断するとPC鋼材が破断することになりますが、この計算式はあくまでも目地部の離間の判別を行うためのもので、途中経過の計算値です。
最終的なPC鋼材の強度確認は目地部が離間する条件により、等価剛性を用いて行われています。 -
問 7.16
後編p.8-35(L2時の照査表)における破壊モードの判定について [1] 最小鉄筋量 100cm×50cm×0.15% = 7.58cm2 < 11.48cm2
[2] 0.517 > 0.330
以上のように、どちらにも該当していないのに破壊モードの判定をしていないのは、何故でしょうか。 - 応答変位法では,靱性を考慮しないので構造物特性係数Csは1.00とします。(後編p.8-35参照)したがって,破壊モードの判定は不要です。
8. シールド
-
問8.1
シールドの管軸方向の計算において等価換算剛性を求める際、コンクリート系セグメントでは、有効断面積を圧縮Ae-c,引張Ae-tとして使い分けています(後編p.11-22の12行目,p.11-27の表3-2最下段)。これに対し、等価中空の断面二次モーメントIeqは、圧縮・引張で同じ値をとるべきなのでしょうか。 - Ieqについては、圧縮・引張で同じ値とすることを計算例集後編p.11-19の27行目,p.11-20の26行目に記載してあるのでご参照ください。
-
問8.2
シールド管きょの応力度照査がNGになるのは、どのような条件のときでしょうか。その場合の対応策には、どのようなものがありますか。 -
シールド管きょの応力度がNGになる可能性としては、鉛直断面よりも管軸方向の場合です。対応策としては、常時で選定したセグメント構造には手を触れずに対処することが望まれます。具体的にはいくつかの方法があり、そのヒントを計算例集後編の本文中に「計算結果に対する考察」として示しているので参照ください。該当ページは次のとおりです。
1) 変位量について p.11-41, p.11-67
2) 管軸方向の応力度について p.11-57, p.11-101
3) 鉛直断面の応力度について p.11-126,p.11-141 -
問8.3
シールド管きょ曲線部の耐震検討方法とその対応策には、どのような方法がありますか。 -
既往の研究事例(建設省土木技術研究所など,下記の参考文献)では、曲線部は標準部に比べて断面力が数倍~20数倍程度までアップすることが推定されています。この傾向は、セグメント径や曲線半径によって変化すると思われます。しかし、個々のケースに応じた具体的評価は、応答変位法の計算だけでは非常に難しく、現時点ではケースバイケースで対応としか言えません。
<参 考>
・川島・杉田・加納;シールドトンネルの耐震性に関する研究 (その7)曲線部を有する下水道シールド管渠に生じる地震力の検討,土木研究所資料第2920号,1990年11月 -
問8.4
マンホールとシールド管きょ接続部の許容値には、具体的な値がありますか。 -
セグメントは、継手部を結合しながら組み立てる構造のため、抜出し量・屈曲角の許容値がありません。
材料自身の構造的基準値がない場合は、当然ですが下水道本来の機能である「流下能力・流下機能」といった機能上の観点から考える必要があります。計算例集後編p.11-41では、浸入水の防止ということから、2mm程度を想定しています。
屈曲角は、経験的に概ね非常に小さい値しか算出されないので、抜出し量の値を優先して評価することになります。 -
問8.5
マンホールとシールド管きょ接続部の抜出し量δは、耐震指針(日本下水道協会)に準拠して、δ=εgd×λで算定しています(εgd;地震動による地盤ひずみ,λ;管の有効長)。しかし、λ =(セグメント幅)ではδが過小評価になると思います。他の考え方(たとえば、1/4波長の長さなど)はないのですか。 -
マンホール接続部の抜出し量を算定する際のシールド有効長ラムダλの取り方については、現行の耐震指針(日本下水道協会)を逸脱しない条件で、(管の有効長 λ )=(セグメント幅B)としました。
将来的な課題としては、[1]シールドの剛性を考慮する,②変位が各セグメントに少しずつ分散されるのなら分散区間分の累積をとる、などが考えられます。
これらのことは計算例集 後編において、[1]はp.11-40,[2]はp.11-67で触れています。 -
問8.6
シールド管きょの鉛直断面にフレーム計算を適用する場合、計算例集では一様剛性なリングを仮定しています。しかし、実際はセグメント継手があるので、その分の剛性低下を考慮する必要はないのでしょうか。もしそうであれば、どの程度のリング剛性(地震時)とすればよいのですか。 -
シールド鉛直断面の応力度計算では、学究的レベルでは、セグメントを千鳥組に組むことを摸して、セグメントの各ピースをはり,継手間をばねとする3次元的な「はり-ばねモデル」による解析方法等も提案されているようです。
しかし、ここでは実務的な計算手法として、リング剛性自身の低下は考えず、その代わり、地盤反力係数を算出する際に管の奥行長をB=10mとして調整をとっています。 -
問8.7
レベル2地震動の鋼製セグメントの応力度照査を簡便に行う手法として、耐震計算例集では、材料の引張強度による照査方法が記載されています。その前提条件としては、材料が破断に至るまでのひずみ量は十分に大きく、破壊に対して安全であるとの判断があるようです(計算例集 後編p.11-80 4-6節)。 しかし、鋼種により応力~ひずみ関係は様々なので、むしろレベル2の応力度照査の際は、引張強度を低減して用いる方が妥当と思います。このような考え方でもいいのですか。 -
ご質問のとおり、シールドの破壊を判断することは、材料の伸び特性が材料ごとに異なることや、地震時に受ける応力場の条件(複合構造体であることに起因する曲げ・せん断などの大きさ)によっても異なるでしょう。しかし、各々の条件に応じた低減には、確立されたものがありません。
仮に、低減が極端に大きい場合(例えば引張強度に対して数分の1)を考えると、これは許容応力度法(レベル1)の設計思想となり、レベル2における限界状態設計法と根本的に異なってしまいます。ですから、低減の大小に関わらず、レベル2で引張強度を低減して照査するといった考え方は、本来の耐震設計の基本思想に反します。
-
問8.8
管路施設については慣性力を考慮する必要はない(計算例集 第1章p.19)のは、管路の挙動が、周辺地盤の変形に支配されるからと解釈できますが、たとえば常時満水状態の管路(セグメント等)では、水の慣性力を考慮する必要はないのでしょうか。 - 管きょは、管の質量(管内の水重量を含む)と管によって置き換えられた地盤の質量との差がほとんどありません。そのため本計算例では、実務上計算の手間を省き簡素化を図る上でも、慣性力は耐震計算上で特に考慮しないこととしました。
-
問8.9
シールド管きょについて、次の計算方法をご教示下さい。
[1] 地盤急変部での管軸方向の応力度の算出
[2] 液状化の沈下による管軸方向の応力度の算出 - 現時点では、両者共に明確な計算方法がありません。管きょの諸元や地盤条件を踏まえ、ケースバイケースで対応します。例えば[1]地盤急変部は、硬質地盤側を固定点とする「はり-ばねモデル」により、管軸方向へ地震力を与えて応力度を求める,[2]液状化による沈下では、スパン両側の非液状化~非液状化を区間長とする「はり-ばねモデル」として両端を固定し、沈下量分の変位を与えて応力度を求める方法などが考えられます。ただし、硬質地盤側・非液状化地盤側を剛結固定とするか、ある程度の値を有するバネ支承とするか等、地盤と管きょの境界条件についても考える必要があります。
-
問8.10
シールド管きょについて、あえて管軸引張側の断面力を低減補正する理由は何でしょうか。 -
地震時のシールドの被害は、世界的に見ても、比較的軽微な損傷は発生しているものの、断面崩壊等の機能を喪失させるような事例はこれまでに報告されていません(下記の参考文献)。これには、次のような理由が考えられます。
[1] 管軸方向に伝わる地震力は、地中内へ分散して減衰しているのではないか?
→たとえば、シールド掘進時のジャッキ推力は、掘進直後は管軸方向にそのまま伝わり、これを支圧壁で受けています。しかしある程度掘進すると、推力はセグメント側面から地盤内へ分散し、支圧壁を必要としません。すなわち、管軸方向へ地震力が伝播する際は、地盤への分散による減衰があると考えられます。
[2] 実際の地盤は不均質なため、地震力は一定に伝わらないのではないか?
→地盤の強度や質的変化の違いは、地震力によってセグメントと地盤の境界面で起こるダイレイタンシー(せん断面における地盤の体積変化)に影響し、地震力を変化させると考えられます。この状態は、シールド本体の挙動、すなわちシールドの剛性にも関係します。
本計算例では、このような地震による被害状況を踏まえ、軸力の補正を考えました。管軸方向の評価の際は、圧縮側・引張側で等価換算剛性の値が異なるので、地震力は両者の剛性の違いにより圧縮力・引張力へ分配されると推定し、等価軸剛性の剛比(EAeq-t/EAeq-c)を関数とする理論をヒントに、実務的ですが引張について低減補正を行いました。
これについて、たとえば0.2などの低減係数が設定できないかとの外部意見もあります。計算を簡素化するためには良い方法なので、今後検討すべき研究課題と思います。
<参 考>
・日本下水道協会;シールド工事用標準セグメント(JSWAS A-3,4-2001),平成13年7月1日改正
-
問8.11
今回の計算例集では、コンクリート系セグメントの軸圧縮剛性を求める際に「水道施設耐震工法指針・解説」に準拠して、ボルトの軸圧縮剛性とセグメントの軸圧縮剛性を直列バネと見なした計算を行っています。ところが、「水道施設耐震工法指針・解説」では、計算例p.320に「軸方向圧縮が作用した場合は、セグメント本体のみで抵抗する」と記述があり、セグメント本体の軸圧縮剛性だけで計算しています。
今回、なぜボルトの剛性までバネ評価したのでしょうか。 -
水道協会の計算例では、圧縮側の曲げ剛性EIeq-cを実験結果等に基づいて低減しています。
今回はこの考え方から派生した考えで、軸圧縮剛性EAeq-cにもバネの評価を行い、剛性を低減したものです。
ただし、ご質問のように圧縮側はセグメント本体としての荷重負担が支配的でしょうから、圧縮側はバネで評価することは不要となる可能性はあります。しかし現在のところ、要・不要の決め方についての詳細はよく分かっていません。 -
問8.12
鉛直断面のフレーム計算の入力データについて、後編p.11-119に節点バネの入力上の注意事項の記載がありますが、これに関連することで質問します。
[1] 後編p.11-118の図7-6(地震時の支点条件)及びp.11-119の図7-7(地盤バネを節点バネとした場合の曲げモーメント)は共に節点バネのような図に見えます。計算のバネとは、部材に一様にかかるバネなのでしょうか。
[2] 分布バネを節点バネに置き換えて計算する場合は、Ks,Kh共にどのように置き換えるのでしょうか(節点分割した各部材長さなどの考慮)。 -
本計算例では地盤バネは部材全体にかかる分布バネとしています。これは、円形管きょに作用する地震水平力を法線・接線方向成分に分解するため、地盤バネも荷重と同一方向にするという考え方からです。よって地盤バネの単位は[kN/m2]であり、バネ値は長さに無関係となります。
分布バネ、節点バネはどちらを使用してもかまいませんが、節点バネを用いる場合はいくつか注意点があります。これらについては計算例集の次の頁を参照ください。
・前編 1.鉄筋コンクリート管(開削用)の 3-4-2節 <参考3-3>,3-4-3節 <参考3-4>
・後編 11.シールド管きょの 7-2-2節 支点条件<図7-7> -
問8.13
7月に日本下水道協会から、「シールド工事用標準セグメントJSWAS A-3,4-2001年版」が発行され、解説編第5章にシールドの耐震設計について記載があります。この基準書と「耐震計算例集」のシールド管きょの内容とは整合しているのでしょうか。 -
「本計算例」と「シールド工事用標準セグメント」の耐震設計についての基本的な考え方は調整しています。しかし、本計算例は実務的な技術書であり、標準セグメントの耐震設計の考え方は現時点までの土木学会の見解です。従いまして、表現は異なっています。
いずれにしましても、本計算例は耐震設計の研究報告書ではありませんので、本計算例以外の考え方を採用されることは全く差し支えありません。別の提案については技術論文等で対外発表し、今後の耐震設計の向上に資することを望みます。
9. マンホール
-
問9.1
矩形人孔の構造計算手法について
[1] 水平断面は版構造か、ラーメン構造か?
[2] 鉛直方向断面照査は長辺方向と短辺方向の両方で必要か?
[3] 大断面の開口がある場合、断面欠損を考慮するか?
[4] 底版の照査方法は? -
[1] ケースバイケースで異なります。常時と同じ考え方で良いと思います。
[2] 長辺方向と短辺方向の両方でチェックする必要があります。
[3] 断面欠損を考慮した統一的耐震計算手法はないのが実状です。常時の検討で開口部の補強を行い、地震時は開口を無視して耐震計算を行う、という割り切りが必要であろうと思われます。
[4] 耐震計算は、水平方向の応答変位を躯体に作用させて耐震検討を行うものであり、頂版や底版には特に地震時荷重を考慮しておりません。したがって、常時の地盤反力や揚圧力の照査を行えば良いこととなります。 -
問9.2
特殊人孔配筋を「土木構造物設計マニュアル(案)」の「ボックスカルバート」に合わせ、主筋と配力筋を従来と逆にする必要性について -
「土木構造物設計マニュアル(案)」は配筋を容易にすることでコスト縮減を図ることを目的にしておりますが、その評価については未だ確立しているとは言えません。従って、その評価が確立するまでは従来の配筋手法でも良いと考えています。
-
問9.3
組立マンホールの耐震計算条件は使用するマンホールにより異なるが、マンホールを特定しない場合の計算条件について -
標準的なマンホールの計算条件は表5-1、表5-3(p.14-47)に示してあります。また、タイプ別のバネ定数は表4-2(p.14-46)に示してあります。継手は大きく3タイプに分けてバネ定数を設定していますが、どのタイプにも属さない継手構造の場合はメーカーにお問い合わせください。
-
問9.4
マンホールの鉛直方向検討時に載荷される地震時荷重は片側載荷となっているが、円形管における両側載荷との違いについて - マンホールの鉛直方向検討時は先端を回転バネとせん断バネで支えられた弾性支承上の直線梁としてモデル化しているのに対し、円形管は周囲を法線方向と接線方向のバネで支承された多節点骨組構造モデルと考えています。マンホールは片側載荷に対し片側バネで支えるモデルであり、両側載荷に対しては両側バネで支えることとなり、計算結果は同じとなります。
-
問9.5
現場打ちマンホールと組立マンホールの組合せ構造の耐震計算手法について - 計算方法としては、組立部と現場打の接合部を適切に評価し、(例えば、回転バネとするか、ピン、ローラーか)モデル化を行えばフレーム計算は可能と考えます。
-
問9.6
組立マンホール計算手法の妥当性と継手バネ値の妥当性について -
兵庫県南部地震の被害状況によると、マンホールの被害については破壊までに至っているものはなかったが、ブロックのズレは多く見られました。
この原因は、マンホールが現在使用されている組立マンホールではなく、従来のブロック間をモルタルで接合したマンホール形式であったと考えております。従って、タイプごとに適切に継手を評価して計算すれば、レベル2相当においても「5参考資料」に示すように、十分な耐力を有するものと考えております。
Aタイプ、Bタイプの継手バネ値は理論値であり、Cタイプのみ実験により求めています。2号、3号マンホールについては、1号の計算結果を内空幅の違いにより換算して算出しています。この考え方は、マンホール工業会で確立されたものであり、この考え方で今のところ問題はないと考えております。 -
問9.7
伏越し部における内圧の考慮について - 地震時の場合には、地震時荷重と内圧の作用方向が相反するため、内圧を考慮しない方が大きな断面力が発生すると考えられます。(内水圧を放射状に与えた場合)但し、内圧が特に大きい場合、あるいは内圧と外圧の比率が特に大きい場合等、種々の計算条件が考えられますので、内圧を考慮した計算によるチェックも場合によっては必要となります。
-
問9.8
マンホールは鉛直方向に直線梁として計算し、処理場の水槽はフレーム計算しているが、その違いについて -
マンホールは深さ方向に棒状の構造物であり、一方、施設は平面的に広がりを持つ構造物であるため、両構造物の特徴を反映した計算手法を採用していると言えます。いわゆる、縦長のものと横長のものの違いと考えられます。構造物によっては、どちらとも言えないようなものも考えられますが、比率による判断基準値はありませんので、微妙な場合は両方で計算した方が良いでしょう。
-
問9.9
矩形マンホールの計算において、(p.13-24)作用する荷重の表中にWbが「-」となり、W3が「+」となっていることについて - 地震時増加荷重Wbは、(応答変位-躯体変位)×地震バネとして求められます。 ここで、躯体変位が応答変位より大きい場合に「-」として算出されます。「-」ということは、反対側から地盤反力が働くということで、Wbの絶対値にWoをプラスすることとなります。
-
問9.10
「2-4-3 地盤反力係数」の算出方法(p.14-14)と「2-4-6 断面力の計算」の算出方法(p.14-19)について -
地盤反力係数は、土層毎の値と節点バネの分担長さで加重平均して算出します。
例えば、節点2の地盤反力係数は以下の通りです。
部材1の分担長さ=0.225m 部材2の分担長さ=0.450m
土層1の範囲=(0.225+0.05)m 土層2の範囲=(0.450-0.05)m
khi = 3133×(0.225+0.05)+7833×(0.450-0.05)/(0.225+0.450)
=5918(kN/m3)
次に、断面力の計算ですが、軸力は節点にかかるブロック重量として計算します。曲げモーメント及びせん断力はp.14-18により算出します。継手回転角は、部材Aのj端回転角と部材Bのi端回転角の差として算出します。継手開口量は、p.14-19式で算出できます。